会社員を辞めてフリーランスになると、必ずついてまわる“税金“と”社会保険”。
あなたは理解できていますか?見て見ぬ振りしていると、痛いしっぺ返しが待ってます。
来年、その税金の金額にびっくりしないよう”今から”税金対策をしておきましょう。
税金対策のポイントは”控除“と”経費“を理解すること。
控除の金額を増やせば、その分、税金の金額は安くなります。
ではどんな控除があるのか?
この記事では、フリーランスが活用できる控除とともに、すぐにできる税金対策を紹介します。
それでは順に解説していきます。
フリーランスの税金対策は?まずは税金の仕組みを知ろう

一言に”税金”といっても様々なものがあります。
フリーランスが自身で収める税金として、主に以下4つがあります。
- 所得税
- 消費税
- 個人事業税
- 住民税
このうち所得税と消費税は「国税」、個人事業税と住民税は「地方税」に該当します。
次に各税金の算出方法を解説します。
なお、消費税の納税は以下に該当する場合は免税されます。
- 開業してから2年間
- 前々年度の課税売上高が1,000万円未満の場合
ですので、会社員を辞めてフリーランスになった直後は、そんなに気にしなくて大丈夫です。
ちなみに、消費税は以下式で算出されます。
フリーランスの税金対策は”控除”と”経費”に着目
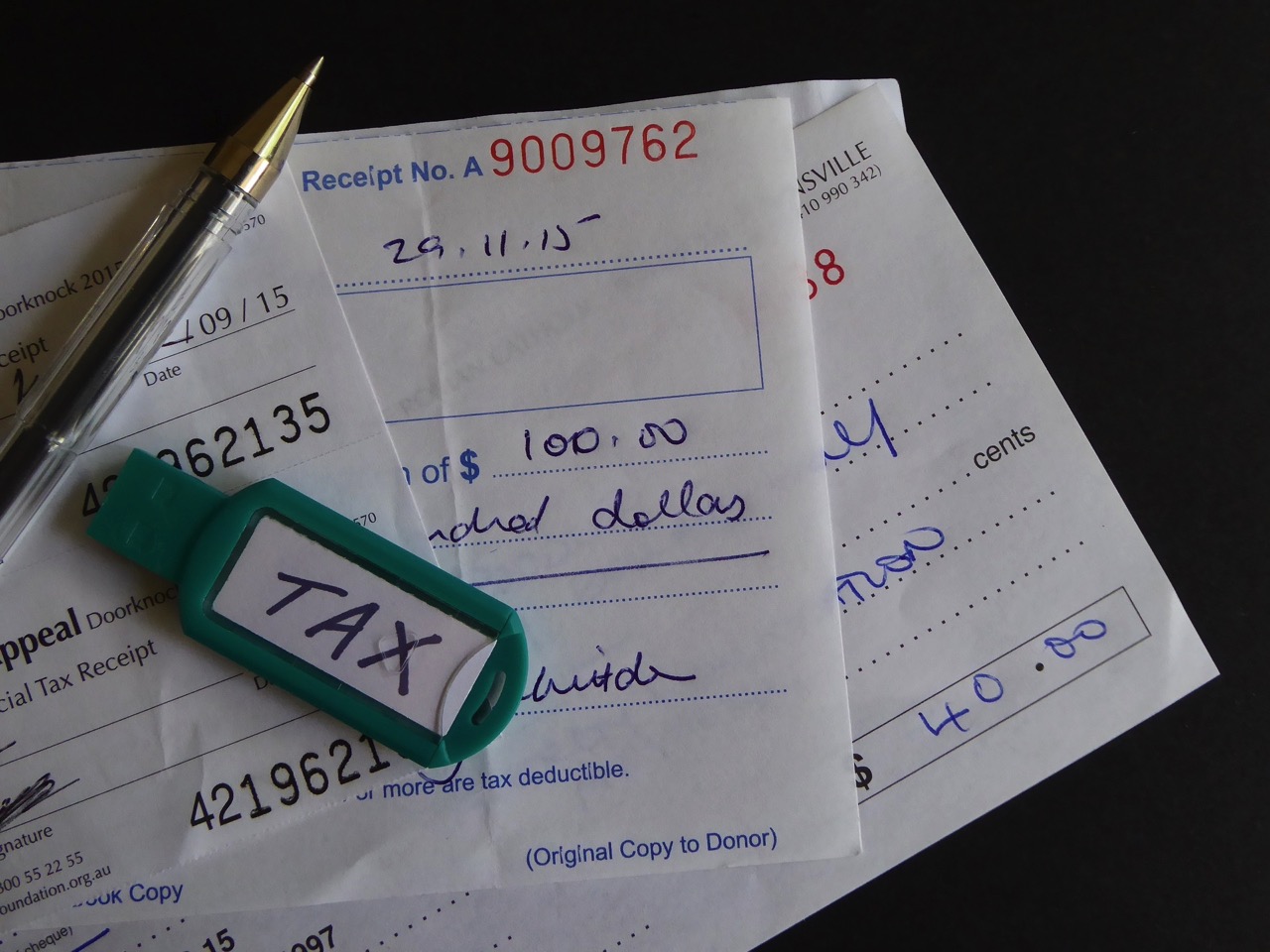
前の項でフリーランスに関係する税金の算出方法を紹介しました。
消費税を除き、各税金の金額はざっくりと以下式にて算出されています。
つまり、税金の金額を減らすポイントは以下2つ。
- 「必要経費」を増やす
- 「各種控除」を増やす
ここでは「各種控除を増やす」に着目して、その方法を紹介します。
そもそも「控除」って何?

「控除」とは”ある金額から一定の金額を差し引くこと“を指します。
それだと広義なので、ここでいう「控除」は”税における控除“を指すことにします。
税における控除とは
税において控除は、一定の要件に該当することで、本来支払うべき税額から若干無税できる金額のことを指し、所得控除など課税標準を計算する途中で控除されるものと、税額控除など課税標準に税率を乗じて計算された金額から控除されるものに大別される。
自分が対象となる控除項目を知り、それを最大限に活用することで、税金の金額を減らすことができます。
もう一度、税金の計算式の共通部分を紹介します。
この「各種控除」には、フリーランスの場合は”所得控除“と”青色申告特別控除“が含まれます。
次にこの「所得控除」と「青色申告特別控除」には、具体的にどんなものがあるか解説します。
所得控除
国税である”所得税”の場合、所得金額から差し引かれる金額(=所得控除)は以下のものがあります。
- 雑損控除
- 医療費控除
- 社会保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 寄附金控除
- 障害者控除
- 寡婦(寡夫)控除
- 勤労学生控除
- 扶養控除
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 基礎控除
参考:国税庁HP「所得金額から差し引かれる金額(所得控除)」
関連記事
青色申告特別控除
青色申告者の特典のひとつで、条件により以下2つの控除を受けられます。
- 65万円の青色申告特別控除
- 10万円の青色申告特別控除
その他
その他の控除として、白色申告の場合のみ「事業専従者控除」があります。
同一生計の配偶者もしくは親族が自身の事業に従事している場合、給与を支払うことがあります。
青色申告の場合、この給与を「専従者給与」として経費にできます。(ただし、一定の要件を満たした場合)
これが白色申告の場合、要件を満たせば一定額控除されます。
フリーランスが税金対策をする場合は基本的に青色申告すると思いますので、”事業専従者控除”は参考程度に覚えておいてください。
フリーランスがすぐに取り組める税金対策はコレ!

多くの控除項目があることを紹介しましたが、フリーランスが”すぐに控除を増やす“ことができる項目は以下4つになります。
- 青色申告特別控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 社会保険料控除
- 寄附金控除
それでは、順に解説していきます。
フリーランスがすぐに取り組める税金対策:青色申告特別控除

青色申告者で、要件を満たした場合は65万円の控除、それ以外は10万円の控除を受けることができます。
65万円の青色申告特別控除
65万円の控除を受ける要件は以下の通り。
- 不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいること
- これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)で記帳していること
- 2.の記帳に基づいて作成した賃借対照表および損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること
10万円の青色申告特別控除
上記①の要件に該当しない青色申告者。
65万円の控除と10万円の控除の違い
この2つの大きな違いは”簿記”となり、以下の違いがあります。
- 65万円控除の場合:複式簿記
- 10万円控除の場合:単式簿記(簡易簿記)
単式簿記は、家計簿のように一つの取引について一つの記録をする方法です。
それに対し複式簿記は、簿記の原則に従ってもっと複雑に記帳する方法です。
“複式簿記”や”賃借対照表”、”損益計算書”など聞きなれない言葉が多いため、65万円の控除を諦めていませんか?
最近は会計ソフトも便利になっており、それほど悩まずにこれらを記帳および出力することができます。
私はfreee ![]() を使っていて、周りのフリーランスの多くも利用している印象です。
を使っていて、周りのフリーランスの多くも利用している印象です。
機能制限はあるものの、今なら無料でお試しができます。
65万円控除と10万円控除の差はとても大きいので、65万円控除に挑戦する方は会計ソフトを導入することを強くおすすめします。
フリーランスがすぐに取り組める税金対策:小規模企業共済等掛金控除

法律で規定された共済契約で掛金等を支払った場合、その掛金は所得控除の対象となります。
フリーランスが契約し掛金を支払うことができるのは、主に以下2つ。
- 小規模企業共済
- 個人型確定拠出年金
いずれも掛金全額が控除の対象となります。
小規模企業共済
小規模企業の経営者や役員、フリーランスなどのための積み立てによる退職金制度。
個人型確定拠出年金(iDeCo)
自分で作る年金制度。
参考:iDeCo公式サイト
フリーランスがすぐに取り組める税金対策:社会保険料控除

自分自身の社会保険料または、配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を納めた場合、その社会保険料は所得控除の対象となります。
控除の対象となる社会保険料は14項目ありますが、そのうちフリーランスが税金対策できるのは「国民年金基金」になります
国民年金基金
厚生年金に加入していないフリーランスにとっての、老後の所得保障の役割を担う制度
参考:国民年金基金HP
フリーランスがすぐに取り組める税金対策:寄附金控除

国や地方公共団体などに対し「特定寄附金」を支出した場合、その支出は所得控除の対象となります。
特定寄附金に該当するものはいくつかありますが、フリーランスが手軽にできるものとして「地方公共団体に対する寄附金(=ふるさと納税)」があります。
参考:国税庁HP:寄附金控除
ふるさと納税
自分の選んだ自治体に寄附を行なった場合に、寄附額のうち2,000円を越える全額が控除される制度。(ただし、一定の上限あり。)
これまでに解説したよう、来年納める税金の金額を減らすには”様々な控除を活用“するのが有効です。
しかし、来年のことより今現在、税金に困っている場合もあると思います。
そんなときは、上記の税金対策をした上で収入を増やすことをおすすめします。
収入が増えると税金の金額が増えますが、案件を獲得してそれ以上に稼ぐしかないです。
フリーランス向けの案件紹介サイトは様々ありますが、私のおすすめはこちら。
Webエンジニアやデザイナー向けの案件が多く掲載されています。
今なら登録は無料です。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
フリーランスに関係する税金は以下4つ挙げられます。
- 所得税
- 消費税
- 個人事業税
- 住民税
税金の金額は”消費税を除き”ざっくりと以下計算式で算出されます。
よって、「必要経費を増やす」ことと「各種控除を増やす」ことが、フリーランスの税金対策として有効です。
フリーランスが「各種控除を増やす」ことをすぐできるのは以下の4つ。
- 青色申告特別控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 社会保険料控除
- 寄附金控除
特に「青色申告特別控除」の65万円控除は大きく、必ず取り組んでもらいたい税金対策です。
そのためには”複式簿記で記帳”などのハードルがありますが、freee ![]() などの会計ソフトをうまく活用しましょう。
などの会計ソフトをうまく活用しましょう。
しかし、来年も大事だけど”いま現在”税金の支払いに悩んでいる方。
その場合は、案件をどんどん獲得して稼ぐしかありません。
いまは苦しいかもしれませんが、ともに頑張りましょう。
この記事があなたにとって少しでもお役に立てれば幸いです。
![]()
